ブログ
紙に綴じの穴をあける
穴あけ台の動画をアップした。
本は、紙に穴をあけて、そこに糸を通すことで作る
(糊を使うパターンもあるが、それはまた書いてみたい)。
その穴をどうやって開けるか、というのは結構、いいテーマだ。
いろいろな可能性が考えられる。
洋風の手製本で使うのは、のこぎり。
折を束にして、よく揃えて、切り込む。目引きと呼ばれる作業だ。
目引き、こんな感じ。
挟むためのプレス(上の動画では手締めプレス)、のこぎり、当てるボール紙などが必要。
そして、歪まないように、きっちり挟むのが難しい。真っ直ぐのこぎりで切るのが難しい。
というわけでちょっと体験したい人には教えにくい。
最近になって、ほぼカッターだけでやる方法に辿り着いた。大学などでは、これを使う。
切り込みによる穴あけ
目引きのいいところは、のこぎりの厚み分、削れて穴があくこと。
カッターで切り込んだだけだと「穴」ではないので、洋風の製本のやりかただと糸の収まるスペースを作ることができない。(逆に和本の列帖装だと、絹糸が食い込んでしっかり止まるので具合がいい。)
上記の、のこぎりでの目引き、カッターで切り込む、のほかに目打ちで開けるというのがある。
これは、子どもワークショップで
針を使わない三つ目綴じ
紙を折る前に穴をあけ、糸で綴じてから折る、という方式。
なぜなら、折ってから折り目に目打ちで穴をあけようとすると、必ずずれてしまうから。
そんな時に、今回動画をアップした穴あけ台が必要になる。
が、使わなくて済むならできるだけ道具が少ない方が、いろんな人ができるだろうと思って、最初はこんな提案をしていた。右下の図。『手で作る本』(P.90、2006年、文化出版局)から。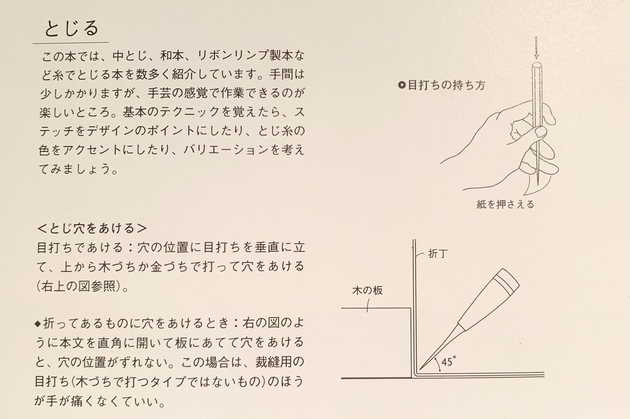
45°などと書いてあるが、これをうまくやるのはけっこう難しい。あとから思いついたのは、全体の下にスチレンボードを敷くこと。そうするとプスッと目打ちの先が刺さるので、ちゃんと穴があく。
まあ、それでも難しさは変わらない。
このスチレンボードが拡張していったのが、こどもワークショップでの段ボールのぐるぐる。
そのあと、箱に詰める方式も作った。
話がいろいろなところに行ってしまうのだが、上の図の右上の図。これは目打ちを木槌などで打つ時の型をあらわしている。六角形をした鉄の鋳物(だと思う)の目打ち。下に木のブロック(木口を上)を置いて打つとスコッと刺さって気持ちがいい。のだが、音が出るのと、やっぱり道具が多くなるので、一般向けワークショップでは使えない。
その点、段ボールの台は音がでないし、木槌も不要なのは大きな利点。
さて、今回の動画をアップ途中に、イギリスの製本の本に紹介されてた方式(真ん中のもの)
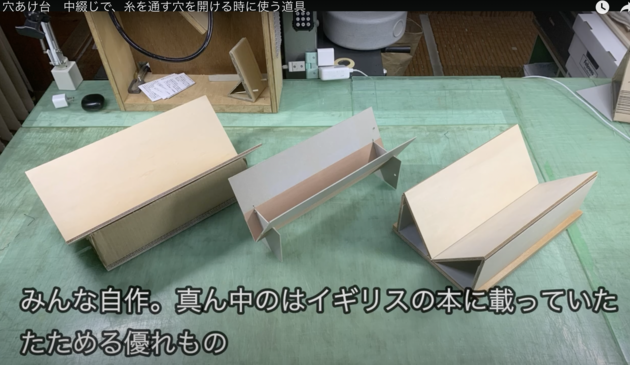 ひさびさに取り出してみて、これもほんとによく工夫されてるなぁ、と思って、それ風でもちょっと作ってみたが、まだ、いまいち。
ひさびさに取り出してみて、これもほんとによく工夫されてるなぁ、と思って、それ風でもちょっと作ってみたが、まだ、いまいち。
あっちへいったり、こっちへ行ったり。
でも、今のところ、今回新しく作った、三角柱二つを組み合わせるのは気に入っている。
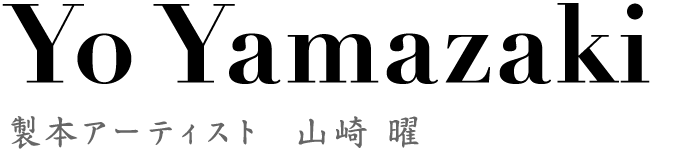
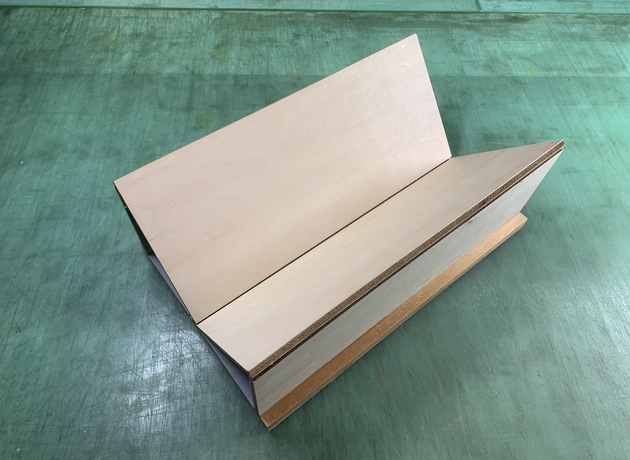
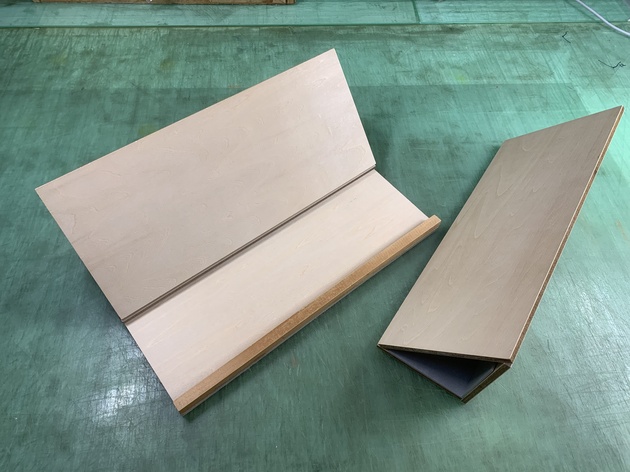
コメントする