ブログ
長方形の切りだし方
しりあがり寿さんの大型本の動画を毎日1~2分の動画にしてアップしてる。
だいたい何日くらいで終わるのか、工程一覧を表にしようと考えていたのだが、やっぱりまだできない。まあ、展示の会期中に終わればうれしい、早く終わっちゃってもいい、終わらなくてもまあいい、と思ってるので、頑張ろうとはしていない。
それはさておき、今の工程は、まだ本文を1ページずつ同じサイズに仕上げ切りしていく段階。
1ページというのは正確ではなく、二つ折の袋折なので、その一つ、そしてM字折と称している四つ折のその一つ、を、一つずつ同じサイズに切る作業をしている。
動画の その5〜その9 までがそれにあたる予定。現時点では、9は明日アップ予定。
↓は、その5 で幅を切っている。下でいうと②の工程。
ここでは、本文紙を切っているが、長方形のものはなんでも同じ。
そして、ほとんどの本と本のパーツは長方形でできているので、あらゆる本のパーツを私は同様の切り方で切っている。
私のこの切り方は、だいぶ前に自分で決めたものだと思っている。習ったのかもしれないが、記憶がはっきりしない。
「この切り方」というのはどういうのかというと、
① 基準の辺(多くの場合、長い一辺)を決める
② ①の基準の辺に対して、もう一つの長辺を平行に切って、長方形の幅を仕上げる
③ ①の基準の辺に対して、接する短辺を直角に切る
④ ③で切った短辺に対して、もう一つの短辺を平行に切って、長方形の高さを仕上げる
いつもは①②③④でやることが多いが、①③②④、①③④②、であってもかまわない。
①より後に②を、①より後に③を、③より後に④をする、という決まり。
こう書くとややこしい。
こう書いてもややこしいし、目の前の人に教えるために説明しても、わかってもらえないことが多いと感じる。
自分にはもはや「体感として自明」になっているので、かえって伝えられないのか。
かなり練習しないと、身体に入らないのは、なんの作業でも同じ、ということか。
去年後半の大学での実習では、このやりかたを諦めて、イラレでプリントした紙を切ってもらったりするやりかたもやっている↓
イラレなどで長方形を描けば、回転してもひっくり返しても、同じ長方形。
あたりまえだ。
私が上で書いたようなやりかたは必要ない。
AIとか小回りの効くカッティングマシンがもう少しだけ進化すれば、サイズを入力すれば切ってもらえるようになる、と思う。今ももうそうなりかかっていると思う。
それもあって、去年からサイズ出し(と、それを書き込むエクセル)にシフトしたような気がする、自分。
上のような切り方になぜなったかというと、製本を学びはじめたころの体験からだ。
表紙の芯の2枚のボール紙を切ろうとして、慎重に細い鉛筆で作図して、その作図に合わせて切り抜いた。しかし、思ったように同じサイズにはならなかった。
どうしたら同じに切れるのか、と考えた結果の成果が上のような切り方。
つまり、基準の角を決める、ということ。
そうすると、ちゃんとした長方形ではないが一つの角を揃えた時にぴったり重なる図形になる。2枚の同じ形をしたボール紙が切れる。
それ以来、私の技法では、基準の角(と基準の辺)、というのがとても重要になったのだった。
そういうのが大事だった時代も終わるのかもと思うと、そういう作業の動画を残しておく、ということに燃えてくる。
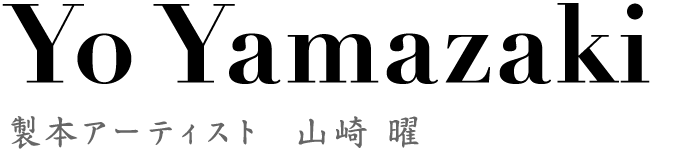
コメントする